『7つの習慣』を読み直し、整理しながら、ゼロをイチにする気づきを記しています。
前回は、少し本題から寄り道して、ヴィクトール・フランクルのナチスドイツ強制収容所での体験をご紹介しました。人間には、刺激と反応の間に「選択の自由」があることが分かりました。
今回からは、「あれば…」にはなりますが、少しずつ、私の体験談も書いていけたらと思います。
目次がありますので、必要なところだけご覧ください
率先力を発揮する
前回の続きになるが、人間は本来「周りの状況に自ら影響を与えることができる」存在である。しかしながら、何気なく生きていると、知らない間にただただ影響を受ける側になってしまう。
とは、
押しつけがましい態度をとるとか、自己中心的になるとか、強引に進めたりすることではない。
進んで行動を起こす責任を自覚することである。
「主体的」についてはこちら
ここで、筆者が転職相談を受ける際のエピソードが紹介されている。
もっと良い仕事に就きたいという人が大勢相談に来る。
私は彼らに必ず、率先力を発揮しなさいとアドバイスする。
彼はさらに、相談者に具体的なアドバイスも与えている。
適性試験を受け、
業界の動向を調べ、
入りたい会社の問題点を探り、解決策を考えプレゼンテーションで売り込む
これらのアプローチに納得できる人は多い。
しかし、率先力を発揮して実施できる人は少なく、実際、望む仕事に就けるのは、主体的に動けるわずかな人だけだと言う。
筆者は子どもに、「RとIを使いなさい」と声をかける。
とは、
Rはresourcefulness=知恵、Iはinitiative=率先力
のこと。
また、主体性を筋肉に例えている。
主体性という筋肉は、たとえ使われずに眠っていても、必ず存在する。
よく主体性が「ある」「ない」という話をするが、そもそも「誰にでもある」ものだと考えたら、「やる」か「やらないか」という主体的な話として見ることができる。
率先力を発揮すれば、自ら機会をつかんだり、問題解決したりすることができる。
体験談:有料級のノウハウを惜しみなく公開する知人
私の体験談をご紹介します。
私の知人でも、自分のノウハウを惜しみなく公開している人がいた。
時間をかけて作り込まれたマニュアルも配っていた。
それも無料で。
私は、これを真似されたら、その人の立場が弱くなるのではないかと考えた。
「どうして、こんなに教えてくれるんですか?」と聞いたところ、
その人は、「実際に行動できる人は、ほとんどいないからです」と、笑顔で答えた。
そしてもちろん、私も・・・。
この知人と話してから8年が経ちますが、今まで一つも行動に移すことはありませんでした。
自分から動くのか、動かされるのか
人生の中で効果性の原則であるP/PCバランスを生み出すには率先力が必要だ。
「7つの習慣」を身につけるにも率先力が要る。
第1の習慣「主体的である」の後に続く六つの習慣を勉強していくと、主体性という筋肉が他の六つの習慣の土台となることが分かるはずだ。
主体性は筋肉に例えられている。つまり、第一の習慣「主体的である」は7つの習慣の土台になる習慣だということだ。
ある団体にコンサルティングをした時の体験が書かれているが、それは割愛する。
企業だけではなく、コミュニティや家庭でも日々問題は起きる。絶望的に見えることもあるし、環境や誰かのせいにすることもある。
しかし、そんな状況の中でも、問いかけを、
「我々はどう反応するのか?我々は何をするのか?この状況で我々はどのように率先力を発揮するのか?」という主体的なテーマに集中することにした。
主語を「我々」に変えると、見方や行動が変わってくるかもしれない。
筆者は、率先力を発揮する人としない人の違いは天と地ほどの開きがあり、さらに自分から動くのか、動かされるのかでも成長や成功の機会が大きく変わると言っている。
言葉に耳を傾ける
私たちの態度と行動は、自分が持っているパラダイムから生み出される。
パラダイムについてはこちら
そして、私たちが普段発している言葉から、主体性の度合いを見ることができるそうだ。
ここで、反応的な言葉と主体的な言葉を見てみよう。
- 私にできることは何もない
- あの人は頭にくる
- 私は……しなければならない
- 私は他のやり方を探す
- 私は気持ちを抑える
- 私は……しよう
続いて、筆者が大学で教えていたときのエピソードが紹介されている。
ある生徒が「テニス合宿があるので、授業を休みたい」と筆者に相談してきた。
筆者は、「行かなければいけないのか、それとも行くのを選ぶのか、どちらか」と問いかけた。
生徒は、「行かなくちゃいけないんです」と答えた。
さらに、「それはなぜか」と問いかけたら、
生徒は、「合宿に行かないことで、チームから外されることがいや」なのだということが分かった。
また、筆者は、同時に授業に参加しないことで起こる結果についても考えさせた。
生徒は、「学ぶ機会を失う」と考えた。
筆者は、それらの結果を比較して、自分の選択を決めなさいと伝えた。
この例で言うと、「合宿に行かなければならない」というのは、反応的な言葉だと言うことが分かる。責任を自分以外のものに置き、自分の反応を選ぶことはできないとしている。
反応的な言葉の厄介なところは、それが自己達成予言になってしまうことだ。
自分はこういう人間だ、私はできない、などと決めてしまうことで、自分の人生の可能性を狭めてしまうことになる。
いつも反応を選択するのは自分であるということを認識しなければならない。自分の日々使っている言葉は大丈夫だろうか。
ここで、愛についてのエピソードも紹介されているが、それについてはまた別に考えてみたい。
体験談:憂鬱な予定、「行きたくない」と「行ったほうがいいかも」の間で…
私の体験談をご紹介します。
私にも行くか行かないか、悩んでいた予定があった。
ぼんやりと「行きたくない」という気持ちがあった。
だが一方で、「行った方がいいかもしれない」、行けば何かいいことがあるかもしれない…とも考えた。
私の師匠に相談したところ、
「このままだとどちらを選んでも後悔だろうから
決めた方に幸多い、と思い込んでみたらいいんじゃないかな?」
と、ありがたいアドバイスをもらうことができた。
私は、まさに、主体的ではなかった。な・さ・す・ぎ・ま・し・た。
行くと決めたのであれば、私は楽しむ努力をする。
行かないと決めたのであれば、私はそのことで何かしらの機会を失うことにも責任を取る。
私には「行く」と「行かない」の二つの選択肢があり、選択肢を選んだあとの反応を選ぶ自由もあったのです。
めっちゃ自由です。私は、少し心が軽くなったように感じました。
※私の師匠については、心の準備が出来次第、いつの日かご紹介する予定です
次へつづく
ここまでのポイント
- 率先力とは、進んで行動を起こす責任を自覚することである
- (筆者の経験から、)自分の望む結果を得ているのは、主体的に行動ができる人である
- 反応的な言葉を日々使っていないか?主体的な言葉を意識しよう
日々目の前に何かは起きますが、まずは「私はどう反応しよう?」と問いかける練習をしてみます。
▶︎次回へつづく
参考:
スティーブン・R・コヴィー,「完訳 7つの習慣 人格主義の回復(新書サイズ) 」,2023年9月,第二部 第1の習慣 主体的である

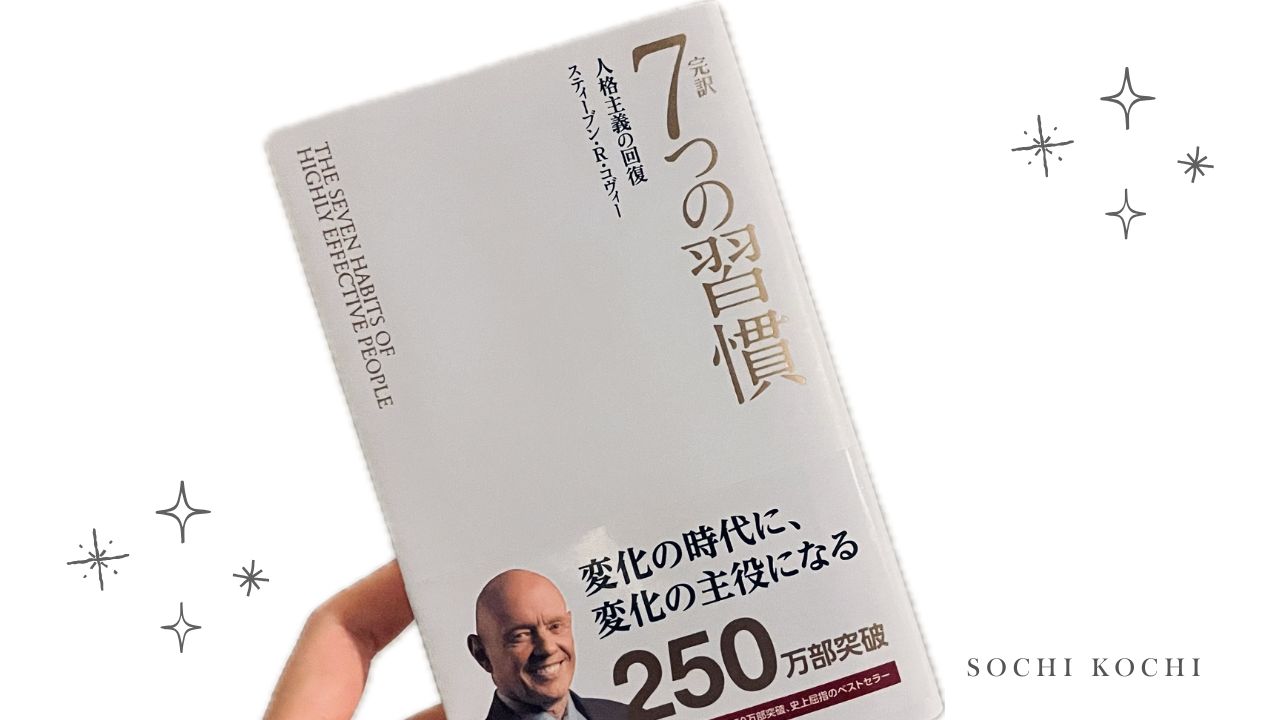



Please leave a comment.