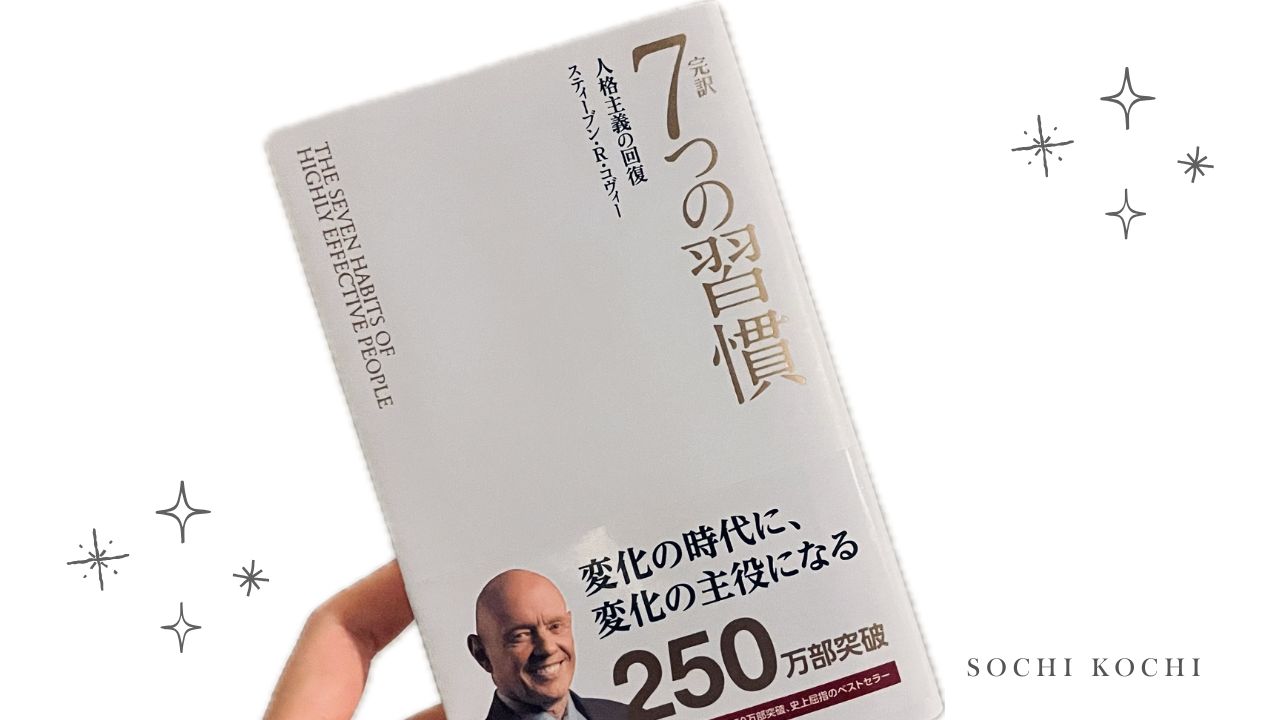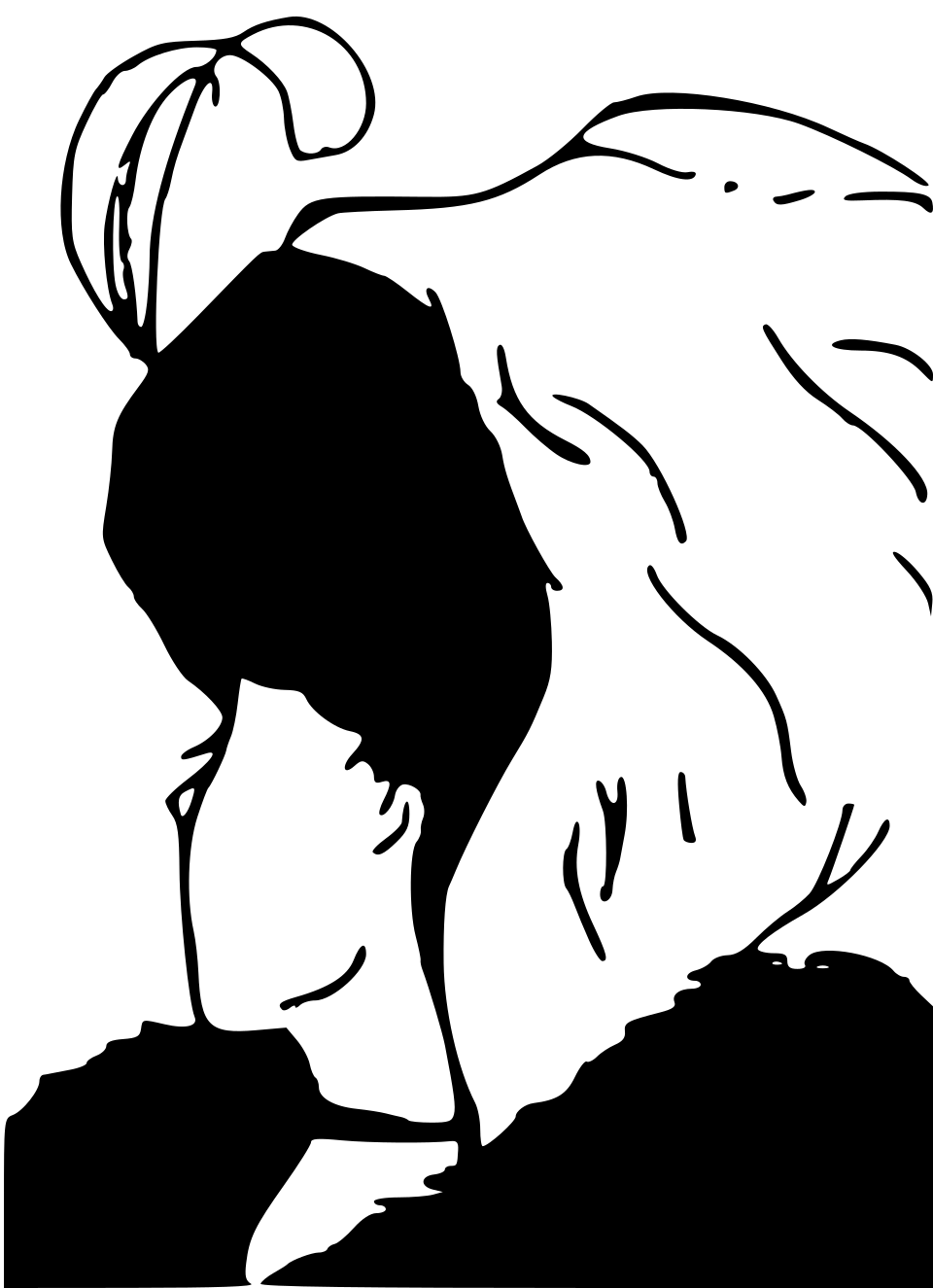『7つの習慣』を読み直していきながら、気づきや感想を記しています。
今回は、第一部「パラダイムと原則」を読み進めていきます。
まずは「インサイド・アウト」について。
読み始めて、有名なスティーブ・ジョブズの「最後の言葉」を思い出しました。
死の床で、ビジネスで成功を築いた喜びより、大切な人との時間を犠牲にしたことに後悔を感じていたという話(ただ、確証があるものではないのだとか…)。このパートは、そのような話から始まります。
まずは自分の理解を深めるためにも、なるべく感想は一旦置いておいて、簡単にまとめていきます。
個性主義と人格主義
とは、
成功は、個性、社会的イメージ、態度・行動、スキル、テクニックなどによって、人間関係を円滑にすることから生まれる
とは、
誠意、謙虚、誠実、勇気、正義、忍耐、勤勉、質素、節制、黄金律など、人間の内面にある人格的なことを成功の条件とする
こう見ると実は、
「個性主義」の方が、社会的にどう見られるかに目を向けており、
「人格主義」は、その人自身の価値を大切にしていることに気づく。
第一の偉大さと、第二の偉大さ
もちろん「個性主義」も有効だが、
本にはあくまでも鎮痛剤のような「応急処置」に過ぎないと書かれている。
寝不足で頭が痛い人がいる
鎮痛剤を使えばその時は楽になるかもしれない
でも、寝不足を辞めなければ、根本的な問題は解決しない
また、翌日頭痛が起きてしまうだろう
生活習慣を整えて(人格主義)、
効果的に鎮痛剤(個性主義)を使う方がうまくいくことには疑いの余地がない。
とは、
優れた人格を持つこと
とは、
才能に対する社会的評価
「無言の人格こそ雄弁」という言葉があるように、
ありのままの人格がどんな言動よりも影響力があるということである。
パラダイムの力・パラダイムシフト
とは、
平たく言えば、物事の「見方」であり、物事をどう認識し、理解し、解釈しているかである
ここで、二つの話が紹介されている。
地図の話
あなたは、シカゴのどこかに行きたい
手元にある地図は、「シカゴ」と表示されている
しかし、それが実はデトロイトの地図だったら、どうだろう
シカゴに辿り着くことはできるだろうか
もしかしたら、なかなか目的地に着かないあなたは、
行動を変えるかもしれない。
「もっと頑張ってスピードを上げよう!」
態度を変えるかもしれない。
「もっと前向きに考えよう!」
でも、それで得られる結果は、
早く、ポジティブに、間違った場所に辿り着けるということだけだけだ、という話。
つまり、個性主義的なテクニックを使ったとしても、
パラダイム(地図)が間違っていれば、目的地には着けないことを伝えている。
だまし絵で行う認知実験の話
次は、ハーバード・ビジネス・スクールの授業で受けた「認知実験の話」。
有名な老人にも若い女性にも見える絵「妻と義母」の話である。
・絵が描かれている二つのカードがある
・学生を二つのグループに分ける
・それぞれのグループに、違うカードを10秒だけ見せる
・そのあと、二つのカードを合成したスクリーンを見ながらお互いに「何を見たか」を説明し合う
・実は、二つのカードには同じ絵が描かれているが、それぞれ色の塗り方だけが変わっていた
・それぞれ、視点が固定化されていたので、なかなか意見が合わない
は、
経験による条件づけが、私たちのものの見方(パラダイム)に強い影響を与えている
若い女性に見えるような色の塗り方をしたカードしか見ていない学生は、どんなに説得されても老婆を見ることができなかったのだ。
態度と行動は自分が持っているパラダイムからうまれることも分かる
例えば、彼女を若い女性だと思い込んでいたら、街で通りを渡ろうとしている時に見かけても手を貸すことはないだろう。
つまり、態度と行動は見方と一致して当然だと言っている。
そして、
他者との接し方もパラダイムの影響を強く受けていることに気づかせてくれる
これまで蓄積された「経験により条件づけられたパラダイム」を見直す必要があるかもしれない。
パラダイムシフトの力/見方とあり方
NYの地下鉄で、1人の男性が子どもを連れて乗り込んできた
子どもたちは大声で騒いでいるが、男性は注意をしない
そこで筆者が声注意をすると、「1時間ほど前に、あのこたちの母親が亡くなって…」と男性が答えた
筆者はこの瞬間に、パラダイムは一瞬にしてシフトしたそうだ。
「アハ体験」だ。
個性主義のテクニックを身につける努力を積んできたところで、
物事が一瞬にして違って見えるパラダイムシフトの大きな変化には比べようもないだろう
パラダイムを変えなければ、態度や行動を変えることは難しいということが分かる。
割愛するが、次に、見方=あり方であるとも書かれている。
原則中心のパラダイム
人格主義の土台となる考え方は、人間の有意義なあり方を支配する原則が存在するということである
は、
- どのような人でも、内面のどこかに必ず潜んでいる
- 原則は手法ではない
- 原則は価値観と異なる
例えば、公正や誠実と正直、可能性などという原則が例に挙げれらているが、まだ明確には「何か」は分からない。
一言で言い表せられるものではないかもしれない。
ただ、『7つの習慣』を読み進める前に、
「原則」は存在すること、
パラダイムをその原則に近づけるほど頭の地図が正しく機能するということを受け止めななければならなさそうだ。
成長と変化の原則
ここでは、応急処置的な「個性主義」の危うさについて書かれている。
すべての生命に、成長と発達のしかるべき順序がある。
テニスの初心者なのに、
カッコよく見せたいために上級者のようにプレーしたらどうだろう
まず、上手くいくはずがない。
「千里の道も一歩から」。
どんなにすごい人でも、誰もが例外なく最初は「初めて」から始めているのだ。
問題の見方こそが問題である
ここでは、部下の士気の低さに悩んでいる上司の話が紹介されている。
「個性主義」的な解決として挙げられていた一例は以下の通り。
- 組織再編や解雇
- モチベーションアップのトレーニング
- もっと有能な人材を見つける
もちろん、それで上手くいくこともあるかもしれない。
ただ、それらを繰り返してもなお、「士気の低い部下ばっかだ…」と、愚痴をこぼしている上司を想像することは難しくない。
上司に対する不信感が士気の低さの原因とは考えられないだろうか。
目の前の問題が解決しない場合、「問題の見方」こそが、問題になっていないだろうか。
筆者は、「人格主義」的な原則に取り組まなければ、根本的な解決も永続的な成果も得られないと言っている。
新しいレベルの思考
アルベルト・アインシュタインの言葉で始まっている。
「我々の直面する重要な問題は、その問題をつくった時と同じ思考のレベルで解決することはできない」
そして、
『7つの習慣』こそが、新しいレベルの思考だと筆者は言っている。
インサイド・アウト
原則を中心に据え、人格を土台とし、インサイド・アウト(内から外へ)のアプローチによって、個人の成長、効果的な人間関係を実現しようという思考である。
とは、
一言で言えば、自分自身の内面から始めるという意味である。
「変わるのは自分から」と、頭では理解していても、なかなか行動を変えるというか変わることは難しい。
まずは自分の内面から始める(インサイド・アウト) ことが大事であること、
人間の有意義なあり方を支配する原則が存在することを受け止めて、『7つの習慣』を読み進めようと思う。
▶︎次回へつづく
参考:
スティーブン・R・コヴィー,「完訳 7つの習慣 人格主義の回復(新書サイズ) 」,2023年9月,第一部インサイド・アウト